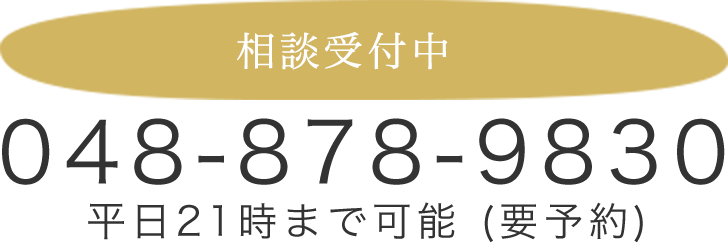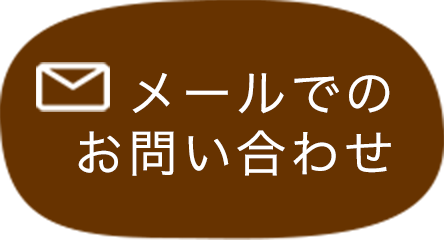自筆証書遺言の書き方
「自分の死後も家族みんなで仲良くしてほしい」という希望をもたれる方は多いと思います。
しかし残念ながら、こうした希望がかなうケースばかりではありません。
相続をめぐって争いが起き、とりかえしのつかないところまで家族関係がこじれてしまう可能性もあります。
こうした相続トラブルを防ぐ有効な手段の1つが、あらかじめ遺言を書いておくことです。
遺言を作成することで、防げる相続トラブルは相当数あります。
自筆証書遺言とは、その名のとおり遺言者本人が自筆で作成した遺言書のことです。
ここでは有効な遺言書を作成するための各要件について説明します。
難しい要件はありませんが、一つも欠けることがないようにご注意ください。
【1】自筆で書かれていること
本文、日付、署名のすべてが自筆で書かれていることが必要です。
第三者の代筆による遺言書はすべて無効になります。
※2019年からは財産目録のみパソコン作成可(目録各項に署名押印等は必要)
【2】日付を記載すること
「2021年1月1日」や「令和3年1月1日」など年月日までの明記が必要です。
※2021年1月吉日では日付特定できないため無効
※複数の遺言書が存在する場合、日付が新しいものが有効となります
【3】署名があること
必ず自書での氏名記載が必要です。
※ゴム印での記載は無効
【4】押印があること
実印、認印、拇印などの押印が必ず必要です。
※実印が最も望ましいといえます
せっかく作成した遺言書が無効になってしまうことのないよう、
自分一人での作成に不安がある場合は、専門家に相談してみることもご検討ください。
なお、遺言の有効性に疑義が生じるのを防ぐために公正証書遺言の作成を選択する方は多いです。
その他のコラム
お墓の管理をめぐって遺産分割協議が大荒れに~思わぬ相続の落とし穴【弁護士解説】
相続手続きの盲点となりがちなのが、お墓の相続です。 特定の相続人が引き受けてくれることになっていればよいのですが、そうでない場合にはお墓の押し付け合いになったり、誰も管理する人がいないお墓が発生したりしてしまうことも……。 こうしたお墓をめぐるトラブルは実務上もそれなりに多く、遺産の問題と一緒に燃え上がるケースもしばしば見られるようです。 今回は意外と難しいお墓の相続について、那賀島弁護士に
遺言の内容に納得できない!遺留分を請求したい【弁護士解説】
故人の遺言が出てきたものの、その内容が特定の誰かに「遺産を全部あげる」というものだったとしたら……。 このような遺言がある場合、「弁護士のところに話が持ち込まれた時点で、そのまま事件化する可能性が高い」と那賀島弁護士は言います。 内容に問題がある遺言が発見された場合、相続人としてはどう対処すればいいのでしょうか。 意外とありがちな「遺言」をめぐるトラブルについて伺いました。
自筆証書遺言の書き方
「自分の死後も家族みんなで仲良くしてほしい」という希望をもたれる方は多いと思います。 しかし残念ながら、こうした希望がかなうケースばかりではありません。 相続をめぐって争いが起き、とりかえしのつかないところまで家族関係がこじれてしまう可能性もあります。 こうした相続トラブルを防ぐ有効な手段の1つが、あらかじめ遺言を書いておくことです。 遺言を作成することで、防げる相
兄弟が親の遺産を使い込んだ!?責任追及はできるか【弁護士解説】
「あると思っていたはずの遺産が全然ない!」となったとき、びっくりしてしまう方が大半だと思います。 実際に財産の管理をしていた人からきちんとした説明があれば納得もできるでしょうが、そうでない場合は「誰かが使い込んだのではないか」という疑念から争いになることも。 今回は、そんな「相続トラブルあるある」ともいうべき遺産の使い込み問題について、那賀島弁護士に伺いました。 事例 私(
老老介護から老老相続へ|相続人・被相続人ともに高齢者の場合に気を付けることは?
高齢化社会の到来により、老老介護が社会問題化しているといいます。 令和4年版の「高齢社会白書」によると令和3年10月1日現在の高齢化率は28.9%。 令和元年度の要介護認定者は655万8000人であり、主な介護者の続柄は配偶者と子どもと子どもの配偶者が半数を占めます。 配偶者による介護はほぼ老老介護に該当しますし、子どもであっても要介護認定者が80歳を超えていれば、老老介護になる可能性は大い