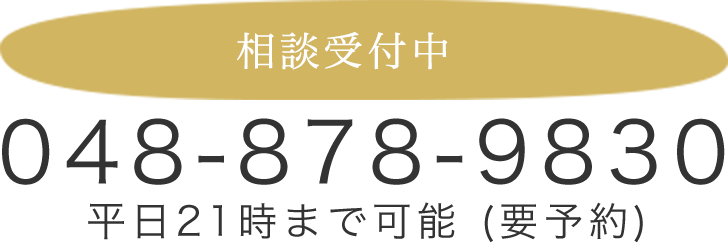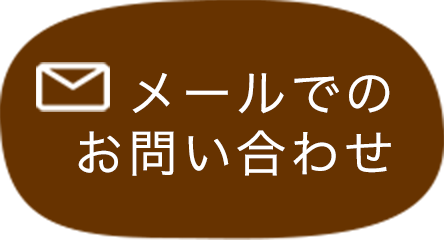兄弟が親の遺産を使い込んだ!?責任追及はできるか【弁護士解説】
「あると思っていたはずの遺産が全然ない!」となったとき、びっくりしてしまう方が大半だと思います。
実際に財産の管理をしていた人からきちんとした説明があれば納得もできるでしょうが、そうでない場合は「誰かが使い込んだのではないか」という疑念から争いになることも。
今回は、そんな「相続トラブルあるある」ともいうべき遺産の使い込み問題について、那賀島弁護士に伺いました。
事例
私(A)は3人姉妹の末っ子です。
母が60歳代で亡くなった後、父は長らく一人暮らしをしていましたが、5年前に認知症になって施設に入りました。
実家の近所には一番上の姉であるBが住んでおり、父が施設に入所するまで時折おかずを届けたり家事を手伝っていたりしていたようです。
また、施設への入所の手続きなどもBが行っていました。
先日父が亡くなり、相続について姉妹で話し合うことになりました。
ところが、Bに通帳を見せられてびっくりしました。
5年前時点で5000万円以上残っていたはずの預貯金が500万円くらいしか残っていなかったのです。
父は大手企業に定年まで勤めていたサラリーマンで、毎月十分な金額の年金をもらっていたはずです。
Bは「施設への入居費などがかかった」と言い訳をするのですが、次姉Cと私は「Bが使い込んだのでは」と疑っています。
私としては、父の面倒を見ていたBに多少多く遺産をあげてもいいと思っていましたが、使い込みがあるとしたら許せません。
使い込まれたお金を取り戻した上で、相続の手続きを進めることはできるでしょうか。
使途不明金は相続トラブルあるある?
ー相続トラブルの大半は遺産の使い込みが絡んでいるという話も聞きます。実際にこうしたケースは多いのでしょうか?
使い込みというか、不透明な支出ですよね。
弁護士の業界では「使途不明金」というのですが、何に使ったのかわからない怪しい出費があると、こうした使途不明金が絡む相続トラブルは非常に多いです。
ただ、一見使い道がわからない出費のように見えても、実は介護の費用などに充てていましたということもあります。
ですので、事例のように急速に財産が目減りしている場合や不透明な支出があった場合、まずは「本当に使い込んだのか」というところを確認していくことが重要になります。
ーなるほど、今回の事例だと預貯金が急激に減っているみたいですが、介護でかかってしまった可能性もゼロではありませんものね。
そうですね。
今回の場合、5年前時点で5000万円残っていたものが500万円になってしまった、ということですよね。
ですから、亡くなるまでの5年間で4500万円をどう使ったのかというところがポイントになるのではと思います。
たとえば富裕層が入るような高級老人ホームに入居していたのであれば、施設で生活するだけで数千万円かかっても仕方ないかもしれません。
ーとなると、介護の実態も含めて調べるということですね。
はい、施設に問い合わせるなり、Bさんに事情を訊くなりして確認すると。
もしかしたら、ここで全部出費の内容に説明がついて、円満に解決することもあるかもしれません。
一方、「施設の費用は全部で1800万円でした」となったら、「じゃあ残りのお金はどうしたんですか」という話になりますよね。
こうした場合、金融機関から入出金履歴を取り寄せて、お金の動きを確認していくことになります。
実際に弁護士に相談する場合も、入出金履歴や施設のパンフレット、相手方の発言を記したメモや録音といった資料を持参していただけるとスムーズです。
ーなるほど。ちなみに下ろした金額や日時はともかく、誰がお金を下ろしたのかの確認ってできるものなんですか?
誰が、というところまではわかりませんが、本人が認知症になっていたり、寝たきりになっていたりすると、自力でお金を下ろせる可能性はゼロですよね。
ということは、少なくとも「本人以外の誰かが下ろしたんですね」という話にはなります。
ーこの事例ですと、少なくとも父親が施設に入ってから後の出金については、父親本人以外の人が下ろした可能性が高い、という推論が成り立ちますね。
個々で問題になるのが、通帳とキャッシュカードを誰が管理していたかということなんですよね。
通帳とキャッシュカードを管理していた人が下ろした可能性が高いという話になってきますので。
もし今回の事例で、Bさんが管理者でしたということであれば、少なくともBは説明をしなければならない立場になりますね。
ー通帳とキャッシュカードの管理ですか……。こういうケースって、施設に入るまで親の面倒を見ていたり、同居していたりした子どもがなし崩し的に管理してしまうパターンが多いんですかね。
そのパターンは多いですね。
それで、もめるケースというのは、お金の管理に関する説明を全部あいまいにしちゃう傾向があるんですよ。
資料も開示せず、これまでの財産の管理状況についての説明もせずに「残っている財産はこれだけです」とやってしまう。
それで、他の相続人が反発してトラブルになるというパターンが多い気がします。
ーこれは、カチンと来るでしょうね。言われた側としては納得できないですし。
多少使い込んじゃったとしても、それも含めて正直に説明してくれる人であれば、まだ円満に解決できる可能性があるんですけどね。
そうはいかないケースの方が多いでしょうね。
怪しい出費の見つけ方
理由のある出費の場合、領収書やノートなどの資料が残っていて、疑われた側もきちんとお金の使い道を説明できることが多いように思います。
ただ、弁護士に相談に来る場合は、お金の使い道が説明できなくてトラブルになっているケースが圧倒的に多いですね。
ー説明されても納得ができない、ということで弁護士マターになるんですね。
そうですね。
ただ、難しいのは説明のできない出費イコール使い込みと決めつけるのも難しいところがあるんですよ。
たとえば、「いつもありがとう。お小遣いで10万円あげるよ」という話が当事者間であって、本人の許可を得てお金を引き出した可能性もあるわけです。
どういう経緯があってお金の引き出しに及んだのかを確認しなければならないですし、それが自然か不自然かということも大事になってきます。
ー自然な出費、不自然な出費の判断基準って、具体的にどんなものなんでしょうか?
まず金額や引き出された間隔ですね。
あとは本人の日記やメモも資料になります。
特に理由もなく、毎日50万円ずつATMで引き出されているとなったら、不自然ですよね。
一方、日記に「今日○○が来て、小遣いとして30万円あげた」みたいな記載があって、実際に30万円の引き出しがあったら、「じゃあお小遣いとしてあげたんですね」という話になる。
ーありそうですね。
今回の事例は施設に入った方の話ですが、難しいのは同居していた時期にかかった生活費ですよね。
一緒に暮らしているとどうしても生活費が混ざってしまいますから。
「月の食費は6、7万円なのに、なぜか50万円下ろされている月がある」といった特殊な事情がないかぎり、使い込みを立証するのは難しいです。
ー孫にお小遣いとしてあげたのかもしれないし、多めに生活費を出す約束をしていたのかもしれないし。
そうそう。
このあたりの事情は証明できないですから。
一緒に暮らしている以上仕方ない、あるいは本人の同意を得て引き出したのではないか、と判断されるケースは多いです。
弁護士からひとこと
使途不明金の問題は当事者間で解決するのが難しい問題です。
問題が残っている間は家庭裁判所の遺産分割調停や審判もストップしてしまうことが一般的なため、問題が発覚した時点で弁護士に相談するのがベストだと思われます。
ただし、使途不明金の問題については相手方と話し合いで解決できない場合は地方裁判所での裁判が必要となり、時間もお金もかかります。
問題になっている金額によっては「あえて裁判をしない」という判断もありうるところです。
弁護士は、具体的な事情と相談者様のご希望を訊いた上でアドバイスや提案を行います。
相談者様が納得のいく判断ができるようサポートいたしますので、まずはご相談いただければと思います。
その他のコラム
「亡くなった親戚の相続人がゼロ問題|財産を相続するためにはどうすればよい?【特別縁故者の申立て】」
国立社会保障・人口問題研究所によると、日本人の50歳時点の未婚者の割合は男性で23.37%、女性は14.06%。 ここには離婚や死別による独身者は含まれません。 未婚=子どもを持っていないという訳ではありませんが、この中の相当数が生涯子どもを持たない方だと推測できます。 結婚もせず、子どもも持たないことによるさまざまな問題が取り沙汰されていますが、相続の現場でも課題が生じることがあります。
兄弟が親の遺産を使い込んだ!?責任追及はできるか【弁護士解説】
「あると思っていたはずの遺産が全然ない!」となったとき、びっくりしてしまう方が大半だと思います。 実際に財産の管理をしていた人からきちんとした説明があれば納得もできるでしょうが、そうでない場合は「誰かが使い込んだのではないか」という疑念から争いになることも。 今回は、そんな「相続トラブルあるある」ともいうべき遺産の使い込み問題について、那賀島弁護士に伺いました。 事例 私(
自営業者・個人事業主のための相続ガイド~事業承継の難しさとその乗り越え方【弁護士解説】
自営業者の相続は事業承継の問題が絡むことが多く、一般の相続に比べてもトラブルが起きやすい傾向があります。 今の事業を次の世代に引き継いでいくためにはどうするべきなのか。 那賀島弁護士に、自営業者ならではの相続問題と適切な対策について伺いました。 事例 私は3人兄弟の末っ子です。 現在は結婚し、県外に出ています。 父は長年、駅前の商店街で洋菓子店を営んでおり、現在は次兄が
自分の遺産をあげたくない子どもがいる場合の相続【弁護士解説】
終活を始めるにあたって、遺言について考える方も多いと思います。 しかし、相続では遺言さえあれば基本的に本人の意思が優先されるとはいえ、本人の希望によっては相続人の反発を招いて「争族」になってしまうリスクも否定できません。 特定の子どもだけに相続させたい、といった不平等な内容の相続を考えている場合は、なおさらです。 今回は、相続させたくない子どもがいる場合に取り
お墓の管理をめぐって遺産分割協議が大荒れに~思わぬ相続の落とし穴【弁護士解説】
相続手続きの盲点となりがちなのが、お墓の相続です。 特定の相続人が引き受けてくれることになっていればよいのですが、そうでない場合にはお墓の押し付け合いになったり、誰も管理する人がいないお墓が発生したりしてしまうことも……。 こうしたお墓をめぐるトラブルは実務上もそれなりに多く、遺産の問題と一緒に燃え上がるケースもしばしば見られるようです。 今回は意外と難しいお墓の相続について、那賀島弁護士に