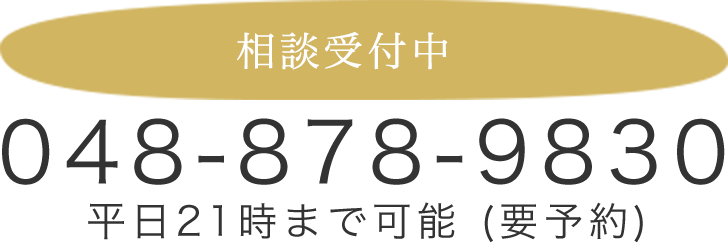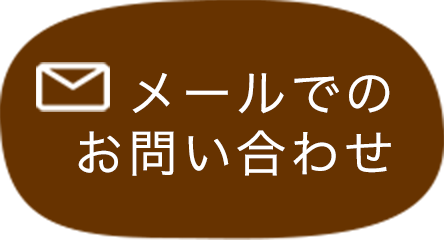内縁・ステップファミリーの相続【弁護士解説】
今の相続制度は法律婚、法律上の親子関係を前提としたものです。
そのため、内縁(事実婚)のカップルやステップファミリーの相続では難しい問題が起きやすいといわれています。
今回は内縁やステップファミリーだからこそ起きる相続トラブルへの対処法について、那賀島弁護士に伺いました。
事例
私は三人姉妹の長女です。
実の両親は早くに離婚し、私は父親に引き取られました。
その後、父親は再婚し、その再婚相手にあたる方が「母」として私を育ててくれました。
ちなみに、妹2人は父親と母の間に生まれた実子です。
家族関係は良好で、母とも実の親子同然に過ごしてきました。
妹2人は遠方に嫁いだため、現在は私が年老いた親の面倒をみています。
ただ、気になっているのは相続のことです。
母と私が血がつながっていないことは、相続にどう影響しますでしょうか。
もし影響するようなら、なんとかしたいと思っています。
内縁・ステップファミリーの相続に関する相談は増加している
ー最近、ステップファミリーが増えているといいますが、もしかして相続の相談も増えているのでしょうか?
そうですね。
私としても、そのような印象を持っています。
配偶者の連れ子と血がつながっていない、さらに養子縁組もしていないとなると、相続のときにトラブルになる可能性がありますから。
前からあったタイプの相談ではあるのですが、最近は家族のあり方が変化しているせいか増えている印象です。
また、家族のあり方の変化に伴う相談といえば、内縁に関する相談も増えています。
最近では法律婚を選ばないカップルも増えてきていますから。
ー先生のところに来る相談はどんなタイプのものが多いでしょうか。
多いのは生前対策ですね。
将来の相続に不安を感じて、という方が多いように思います。
もちろん相続が起きたあとで相談に来られる方もいます。
しかし、残念ながら、そういう方の場合は納得の行く解決を図るのはなかなか難しい。
やはり内縁やステップファミリーの相続では、遺言を書いたり贈与をしたりといった生前対策が大事なんですよ。
ー生前対策をしておかないと手遅れになってしまうリスクが高いということですね。
ステップファミリーの生前対策
ー生前対策としてはどのようなものが考えられるでしょうか。
今回のようなステップファミリーのケースでいえば養子縁組でしょうね。
遺言で財産をあげるよりも、養子縁組して相続人になれるのが一番いいわけですから。
それですべて解決です。
紙切れ一枚書けばできる手続きなので、手続きする側の苦労もそんなにないと思うんですけどね。
ーたとえば今回のケースだと、同じ姉妹であるにも関わらず、妹だけがお母さんの実子ということで相続時には姉妹間で大きな格差が発生してしまいます。
相談者もお母さんの養子になれば、そのあたりの問題は解決できるわけですね。
そうですね。
相続で妹さんとモメる可能性は相当減らせると思います。
養子縁組をしたときの状況によってはトラブルが起きる可能性はありますが、お母さんが元気なうちに「長女も私の娘だから」といって養子にしてくれれば妹さんも納得しやすいでしょう。
トラブルは起きにくいと思います。
ーええと、「元気なうちに」ということは、裏を返すと「元気じゃないとき」……たとえば認知症の症状が出始めたタイミングで養子にしてしまった場合なんかには問題になるということでしょうか。
養子縁組の効果が争われるリスクは出てくるでしょうね。
養子縁組のような身分行為は本人の意思が非常に重視されますので、売買のような財産行為よりは有効性が認められやすいとは思いますが、リスクといえばリスクです。
認知症の程度にもよりますが、場合によっては無効になってしまう可能性もないとはいえない。
ーなるほど。
ちなみに、生前対策として出てきた養子縁組の話ですけど、デメリットってありますか?一般的には「一度縁組してしまうと離縁が難しい」といったデメリットがあると言われているようですが……。
たしかに、養子縁組の場合、養親・養子双方が同意できていない限りは離縁は難しいという側面はあります。
たとえば配偶者の連れ子と養子縁組したものの、すぐに結婚生活が破綻してしまったといったケース、これは養子との関係をどうするかをめぐってモメるでしょうね。
特に資産家と養子縁組しているケースだと、子ども側も離縁したくないと思うかもしれませんし。
裁判で争うという可能性も十分考えられるでしょう。
ただ、今回のような育ての母と子どもとの間の養子縁組だと、よほどのことがない限り「離縁しよう」という話は出てこないと思いますよ。
ーたしかに…。
ただ、実際にご相談を聞いていると、実の子と連れ子とで扱いを変えるという人もいるみたいですので、そこはなんとも言えないところではあります。
義理のお母さんが養子縁組を拒んでいる場合、もしかしたら自分の子どもにだけ財産を残したいという気持ちがあるのかもしれないですね。
だとすると、もうどうしようもないという話になってきてしまいますね。
非常に心苦しいですが……。
ー養子縁組以外の方法としては、どんなものがあるでしょうか?
遺言や生前贈与が考えられます。
ただ、これも本人が認知症になってしまってしまうと難しいですね。
本人が遺言を書く前に認知症になってしまったり、何も生前対策をしないまま亡くなってしまったり、といった事態になると、血のつながらない子どもの側としてはどうしようもない。
もちろん実親の配偶者は法律上は親族になりますので、故人を献身的に介護したような場合には相続人に対して特別寄与料を請求できる可能性があります。
ただ、これも立証の難しさを考慮すると、結構険しい道になるでしょうね。
内縁カップルの場合は?
ーここまで、ステップファミリーの話をしてきましたが、内縁……法律婚をしていないカップルの場合はどうでしょうか?相続権がないという意味では、血のつながりがない「連れ子」と似たような問題が発生すると思うのですが。
何らかの事情で法律婚ができない、しないという方は昔からいらっしゃいます。
最近増えているのは、熟年離婚後に新しいパートナーを見つけたようなケースですね。
こういうケースだとお互い子どもがいたりするので、子どもの手前、籍は入れないで事実婚にしたいと。
そういうカップルからのご相談は最近増えていますね。
ーそれも生前対策でしょうか?
そうですね。
「2人で住んでいる家はどちらかに残したい」ということでご相談に来られる方が多いですね。
内縁の場合は相続権も配偶者居住権もないので、何もしないまま一方が亡くなると2人で買ったマイホームをパートナーに残せない。
自分名義の不動産にパートナーと住んでいた場合は、自分の死後、パートナーが相続人に追い出されてしまう可能性もあります。
ーなかなか過酷ですね……。
年老いてからマイホームから追い出されてしまうと、精神的にも肉体的にも相当きついと思います。
そうなんですよ。
だから、遺言を書いて遺贈したり、あるいは生前贈与をしたりして、なんとか住む家をパートナーに残してあげる必要があるわけですね。
ーなるほど。
ちなみに遺贈と生前贈与、どちらがいいのでしょうか?
これはケースバイケースですが、シンプルなのは贈与ではないでしょうか。
早めに生前贈与してもらえば、遺留分を相続人から請求されるリスクも低くなります。
たとえば不動産の名義が男性だったら、平均余命が長い女性側に不動産を贈与してもらう。
ただ、贈与の場合、贈与税が高いんですよね。
高い贈与税を払うか、あとで遺留分を支払うのとどちらが得なのか。
現金や預貯金などの流動資産も考慮しながら、その方に合った方法を考える必要があります。
ーなるほど。
なかなか難しいですね……。
税理士の先生や司法書士の先生と連携して手続きを進めていく必要がありますね。
さらに、贈与で不動産をもらった女性側が早く亡くなってしまうリスクを考慮して、プラスアルファで「パートナーである男性に不動産を遺贈する」という遺言を書いてもらう。
そうじゃないと、もしものことがあった場合に、女性側の親族に不動産がいってしまう可能性があるので。
ー不動産が行って戻る……というイメージでしょうか。
なかなか奥が深いですね。
そうなんです。
結構奥が深い話なんですよ。
このあたりは弁護士の腕の見せどころといえるでしょうね。
内縁のカップルが難しいのは、相続時には自分の子どもとパートナーが対立する関係になってしまう可能性があることです。
ーお互いに子どもがいなければいいんでしょうけど……。
子どもに限らず相続人がいる場合は、何も手も打たずに亡くなると相続人との間にトラブルになる可能性が高いといえます。
法律婚ではない形を選んだ場合は、将来のことについて2人でよく話し合っておくべきだと思います。
この問題を乗り越えられないと、カップルそのものが破局しかねません。
ー早めの相談が重要ということですね。
弁護士からひとこと
家族のかたちが多様化するとともに、ステップファミリーや事実婚という家族の形を選ぶ人も増えています。
しかし、今の民法の規定では配偶者の連れ子や内縁(事実婚)のパートナーには相続権が認められていません。
そのため、遺言や生前贈与といった生前対策をしておかないと、相続が起きたときにトラブルが起きやすくなってしまいます。
生前対策をする場合、本人が元気なうちに行う必要があります。
相続に少しでも不安を感じた時点で早めに相談に来ていただければと思います。
その他のコラム
障害の子どもの未来を守る相続の形とは~想定されるリスクと家族が行うべき準備【弁護士解説】
障害を持つお子さんを持つ家庭の相続には、一般家庭とは異なる課題を持っています。 障害を持つお子さんを持つ親にとって、相続の準備はただの法的手続きではなく、お子さんの未来を守るための重要なステップです。 お子さんの平穏な生活を守るためにいったい何をすればいいのか。 今回は那賀島弁護士に、その具体的な方法や注意点を伺いました。 事例 わたしは60代の男性です。 妻と子どもが
遺言の内容に納得できない!遺留分を請求したい【弁護士解説】
故人の遺言が出てきたものの、その内容が特定の誰かに「遺産を全部あげる」というものだったとしたら……。 このような遺言がある場合、「弁護士のところに話が持ち込まれた時点で、そのまま事件化する可能性が高い」と那賀島弁護士は言います。 内容に問題がある遺言が発見された場合、相続人としてはどう対処すればいいのでしょうか。 意外とありがちな「遺言」をめぐるトラブルについて伺いました。
内縁・ステップファミリーの相続【弁護士解説】
今の相続制度は法律婚、法律上の親子関係を前提としたものです。 そのため、内縁(事実婚)のカップルやステップファミリーの相続では難しい問題が起きやすいといわれています。 今回は内縁やステップファミリーだからこそ起きる相続トラブルへの対処法について、那賀島弁護士に伺いました。 事例 私は三人姉妹の長女です。 実の両親は早くに離婚し、私は父親に引き取られました。 その後、父親
「長男だから遺産を全部ほしい」という言い分は通る?【弁護士解説】
現在の法律では、相続で子どもは全員平等です。 ところが、実際には法律のとおり、スムーズに話し合いが進むケースばかりではないようです。 「長男だから全部遺産はもらう」「親に遺産をもらう約束をした」と言い張る兄弟がいた場合、残りの兄弟姉妹としてはどう対応すればいいのでしょうか。 「俺は長男だから!」と主張する兄弟がいた場合の相続について、那賀島弁護士に伺いました。
不動産の相続をスムーズに進めるためにはどうすればいいですか?【弁護士解説】
相続財産の中に不動産が含まれる場合、相続財産全体の価額に占める不動産の割合や相続人の懐具合によっては、不動産の価額などをめぐって「争族」になってしまう可能性があります。 なぜ不動産の相続は大変なのか、スムーズに話し合いを進めるためにはどうすればいいのか……不動産相続の注意点について那賀島弁護士に伺いました。 事例 都内近郊で一人暮らしをしていた父親が亡くなり、