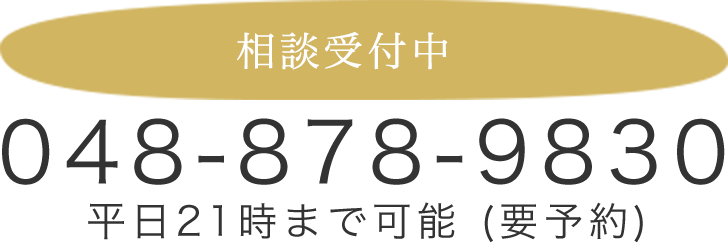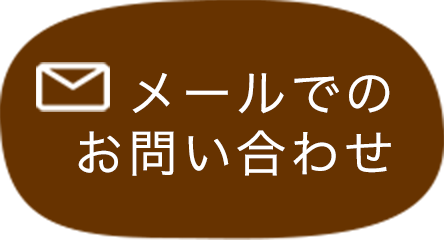配偶者居住権とは?ステップファミリーの増加で出番が増える?【弁護士解説】
平成30年の相続法改正でスタートした配偶者居住権制度。
夫(妻)に先立たれた配偶者の暮らしを守るための制度ですが、実際の使い勝手はどうなのでしょうか。
制度の概要や使い所、今後の展望などについて、那賀島弁護士に伺いました。
事例
私は70代の女性です。
先日、35年間連れ添ってきた夫が突然亡くなりました。
相続人は私、私と夫の子ども1人、そして夫が前妻との間に子どもが2人います。
財産は自宅マンション(3000万円相当)、預貯金1000万円があります。
遺言はありません。
私としてはできればこのまま住み慣れた自宅に住み続けたいと思っています。
私の希望は叶うでしょうか?
そもそも配偶者居住権とは
ー平成30年の法改正で、新しく配偶者居住権という制度が始まったと聞きました。
そもそもどんな制度なのでしょうか?
配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が住み慣れた自宅に無償で住み続けられるという権利です。
亡くなるまで居住権を設定することもできますし、自宅をもらった場合よりも財産の評価額を下げることができます。
ー具体的に、配偶者居住権が使える場面ってどんなケースなのでしょうか。
現金が少なくて、建物を奪い合うようなケースが典型例ではないでしょうか。
たとえば、父親が亡くなって、母親と子供が相続人になったとします。
母親は住み慣れた自宅に住み続けることを希望しているけれど、自宅以外の資産があまりないと。
そういうときに母親が自宅の所有権をもらってしまうと、他の相続人に代償金を払わないといけなくなるわけです。
ー子どもが遠慮して、相続放棄をしてくれないかぎりは……。
そうですね。
代償金として現金を1000万、2000万円支払うとなると、やはり経済的に大変なわけです。
しかし、これが居住権になると、建物所有権よりは経済的な価値が下がります。
もしかしたら代償金を支払わなくて済むかもしれないですし、場合によっては残りの資産……たとえば預貯金の取り分も増えるかもしれない。
ーしかも、死ぬまでタダで自宅に住むこともできると。
残された配偶者にとってはメリットが大きい制度ですね。
そうですね。
配偶者居住権の登場は、平成30年の相続法改正の中でも重要な改正のひとつだと思います。
相続が起きたばかりに「住み慣れた自宅を売らなければいけない」となると、高齢の方にとっては負担がかかります。
この制度ができる前は、苦労していた方も多いと思いますよ。
配偶者居住権の実際
ー制度が始まって5年以上経過しましたが、実際の活用状況はどうなのでしょうか。
あくまでも個人的な体感ですが、今のところそこまで積極的に活用されているとは言い難いかもしれません。
私自身、相続問題に数多く取り組んでいますが、今のところ配偶者居住権を主張したことも主張されたこともないんですよね。
ー意外です。
鳴り物入りで制度化されたからには、てっきりバンバン活用されているものだと思っていました。
というのも、親が亡くなって子どもたちが相続でモメるというパターンが多くて、配偶者込みでモメているパターンがそんなに多くないからかもしれません。
ーなるほど。
もちろん配偶者居住権自体は重要な制度だと思いますので、弁護士としては日頃から相当勉強してはいます。
ただ、今のところ配偶者居住権を主張するようなケースにはあたっていないという感じでしょうか。
ーなんだかわかるような気がします。
実の親子同士だと、なんとなく親に遠慮してしまうというか。
おっしゃるとおりで、そういう傾向はあると思いますね。
一方、親が再婚しているようなケースでは、配偶者居住権を使う余地が出てくると思います。
ーまさに今回の事例ですね。
はい。
親の再婚相手と子どもたちの関係がよくないと、どうしても相続の場でトラブルになりやすくなりますから。
最近ではステップファミリーも増えていますよね。
もしかしたら今後、配偶者居住権が関係する相続トラブルが増えてくるかもしれません。
配偶者居住権の評価額はどうやって計算する?
ー配偶者居住権を取得すると、不動産そのものの所有権をもらうのと比べて評価額が下げられるんですよね。
とはいえ、不動産を無料で使い続けられるなんて、ものすごく財産的な価値がある権利だと思うんです。
素人考えだと、結構、評価額は高いんじゃないかというイメージがあります。
実際のところ、配偶者居住権の評価額ってどれくらいなんですか?
配偶者居住権の評価額については、日本不動産鑑定士協会連合会が公表している算定方法が参考になります。
まず、固定資産税評価額や法定耐用年数、配偶者居住権の存続年数などをもとに、配偶者居住権がついている不動産の所有権の評価額を求めます。
こうして所有権の評価額を、不動産そのものの評価額から引いた差額が配偶者居住権の評価額です。
ーすいません。
お話伺っていて、ものすごくややこしいと思ってしまったんですが……。
そうなんですよ。
一般の方が自力で計算するのはなかなか難しいのではないでしょうか。
もっと言ってしまうと、遺産調停の場で配偶者居住権の主張が出た場合、「配偶者居住権の価値がいくらなのか」「そもそも不動産そのものの価値はいくらなのか」ということをめぐって、相続人同士で意見が対立する可能性が高いです。
誰かが折れない限りは、最終的に不動産の鑑定で決着をつけるということになるんでしょうけれど。
ー不動産の鑑定ですか。
不動産の鑑定って、費用がかかると伺ったのですが……。
そうですね。
場合によっては、百万円単位での出費を覚悟しなければいけないこともあると思いますよ。
できれば相続が起きる前に弁護士に相談を
ー配偶者居住権を主張するのって大変ですね……。
そうですね。
不動産関係の費用などもかかってしまいますし、しなくて済めばベストではあります。
そもそも、こういった問題って、被相続人の方が遺言や生前贈与といった生前対策をしておけば避けられたトラブルではあるんですよね。
今回の事例も遺言や生前贈与をしておけばよかったケースではあることは間違いないと思います。
ーたしかに、遺言や生前贈与のほうが、手続きとしては簡単だなと思いました。
「生前対策してくださいね」と言うと「私にはまだ早い」「必要ない」という方もいらっしゃるのですが、トラブルを避けるためにも必要なことだと思います。
今回のような血がつながらない子どもがいるような場合では特に重要ですね。
ー遺言があるだけで防げるトラブルもあると。
先生も常に「遺言を書いてください。できれば5年に一度は書き直してください」とおっしゃっていますよね。
大事なことですから。
ここでも改めて強調したいと思います。
ただ、遺言や生前贈与も場合によっては遺留分の問題が起きてしまいます。
生前対策をする場合も、まずは弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士からひとこと
ステップファミリーをめぐる相続では、遺言や生前贈与といった生前対策が非常に重要になります。
家族関係の問題から、相続人同士の意見が対立しやすいからです。
今回の事例のようなケースでも、遺言があれば比較的スムーズに相続の手続きが進んだのではないでしょうか。
ただし、万が一遺言がなかった場合であっても、残された配偶者が配偶者居住権を主張することで自宅を追い出されずに済むというケースはあると思われます。
遺言や生前贈与が間に合わなかった場合も、まずは諦めずにご相談いただければと思います。
その他のコラム
「長男だから遺産を全部ほしい」という言い分は通る?【弁護士解説】
現在の法律では、相続で子どもは全員平等です。 ところが、実際には法律のとおり、スムーズに話し合いが進むケースばかりではないようです。 「長男だから全部遺産はもらう」「親に遺産をもらう約束をした」と言い張る兄弟がいた場合、残りの兄弟姉妹としてはどう対応すればいいのでしょうか。 「俺は長男だから!」と主張する兄弟がいた場合の相続について、那賀島弁護士に伺いました。
相続放棄の落とし穴【弁護士解説】
相続放棄は相続をしないと決めることをいいます。 相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったという扱いになるため、プラスの財産を相続できない代わりに借金も相続しなくても済みます。 そのため、「故人に借金がある場合は相続放棄を選択肢に入れるべき」と那賀島弁護士は言います。 ただ、相続放棄をしようにもいろいろ落とし穴があるようで……。 そこで、今回は簡単そうで意外と難しい(?)相続放棄の落とし
障害の子どもの未来を守る相続の形とは~想定されるリスクと家族が行うべき準備【弁護士解説】
障害を持つお子さんを持つ家庭の相続には、一般家庭とは異なる課題を持っています。 障害を持つお子さんを持つ親にとって、相続の準備はただの法的手続きではなく、お子さんの未来を守るための重要なステップです。 お子さんの平穏な生活を守るためにいったい何をすればいいのか。 今回は那賀島弁護士に、その具体的な方法や注意点を伺いました。 事例 わたしは60代の男性です。 妻と子どもが
【地方親×都市圏の子ども】弁護士に聞く〜相続で困らないために知っておくべきこと〜
地方在住の子どもたちが就職や進学をきっかけに、都市部や首都圏に出て行く。そんな光景は珍しくありません。今や親子が離れて暮らすことで大きな不便を感じることはあまりないかもしれません。ところが物理的に離れた場所で相続が発生すると、さまざまな不都合が生じることが。そこで今回は当事務所の那賀島弁護士に「離れて暮らす家族や親戚で発生した相続のトラブル」について伺いました。 親の近くに住んで
【弁護士が語る!】私たち、これで困りました!実録相続トラブル
相続は「争族」と書かれるほどにトラブルが多いと耳にすることがあるかと思います。たしかにテレビの再現VTRやドラマ、漫画では相続で揉める家族が頻繁に登場します。しかし「うちは大丈夫でしょう」と考えている方が多いのではないでしょうか。相続で揉めるのは資産家ばかりでは?と思っている方も少なくありません。でも実際に事務所を訪れるのはごく普通のご家族が多いんです。 そこで今回は、当事務所の