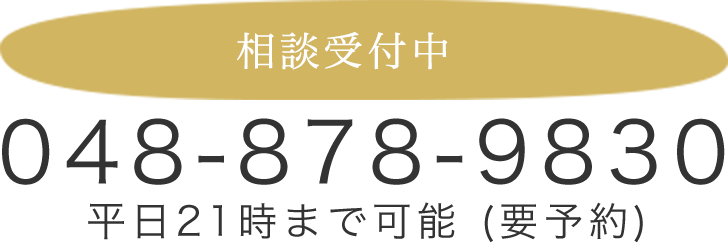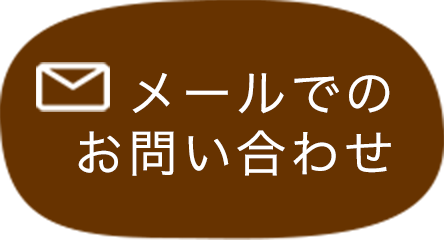相続放棄の落とし穴【弁護士解説】
相続放棄は相続をしないと決めることをいいます。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったという扱いになるため、プラスの財産を相続できない代わりに借金も相続しなくても済みます。
そのため、「故人に借金がある場合は相続放棄を選択肢に入れるべき」と那賀島弁護士は言います。
ただ、相続放棄をしようにもいろいろ落とし穴があるようで……。
そこで、今回は簡単そうで意外と難しい(?)相続放棄の落とし穴について那賀島弁護士に伺いました。
事例
私は4人兄弟の末っ子です。
この間、地方で一人暮らしをしていた父親が亡くなり、相続が発生しました。
遺言はありません。
四十九日の法要で集まった際に、父親とともに農業を営んでいた長兄から「土地以外の財産がほとんどない」「金融機関から借り入れがある」旨を告げられ、暗に相続放棄したほうがいいのではとすすめられました。
私はこのまま相続放棄してもいいのでしょうか。
ちなみに長男と折り合いの悪い次兄は「俺は放棄しない」と言い張っており、兄弟間で意見が分かれています。
このままだとおそらく相続でモメそうです。
相続放棄の相談で多いパターンとは
相続放棄の問題で法律事務所に来る場合、財産はゼロで借金だけが残っているというパターンがほとんどのように思います。
今回の事例のように農地を残しているというのはまだマシです。
家は賃貸でゴミ屋敷、残ったのは借金だけというパターンが多いですね。
ーなるほど。
田舎の農地であっても、土地が残っているだけまだマシなんですね。
故人がきちんと暮らしていて、財産分与の余地があるという意味ではいいことですよね。
ただ、「相続放棄をしてもいいか」という意味では今回の事例は悩ましいと思います。
相続放棄で一般的なのは、故人が借金を残していて預貯金や不動産といった財産もなくて……というわかりやすいパターンです。
この場合、とるべき選択は「相続放棄一択」ということでスッキリ解決します。
一方、今回のケースのように、プラスの財産もあるけど借金がいくらあるのかわからないという状態だと、相続放棄するのがベストな選択かどうか判断がつきにくいですよね。
特に、「長男が跡取り」という意識が強い家庭だと、「俺は跡取りで全部もらうから」ということで長男が財産をつまびらかにしてくれない場合も多いです。
ーなるほど……。
他の兄弟としては不満が溜まりますよね。
一方的に説明されても納得できないというか。
そうですね。
実際、「長男側がきちんと財産をオープンにしてくれれば相続放棄するのに、オープンにしてくれないから相続放棄していいのかわからない」と困っている方は結構いらっしゃいますよ。
ですから、こうした場合は財産の内容をきちんと調査して、相続放棄するべきかどうか確かめる必要があります。
知らないと損をする!?相続放棄の落とし穴
ー長男側の態度次第で、だいぶ相続の手続きの難易度が変わってくると。
そういえば地方だと、長男以外は相続放棄するみたいな習慣が根付いているところもあるみたいですよね。
あるかもしれませんね。
ただ、相手の言い分が正しいとは限らないので、「相続放棄しろ」と言われて納得できないようなら、その場で対応を決めず、弁護士のところに相談に来てほしいなと思います。
というのも、「相続放棄」の問題を考える上では、いくつか注意しなければいけないポイントがあるからです。
まず、一般の方が考える「相続放棄」が、法律的な意味での相続放棄とズレている可能性があります。
よく遺産分割協議のときに、「相続放棄をしろ」と言われて判子を押した、押させられた、という話が出てきますよね。
あれは、厳密に言えば、相続放棄ではないんです。
相続分の放棄、つまり、「あなたの相続分をゼロにします」という遺産分割協議をしましたよ、ということなんですよ。
ーなるほど。
遺産分割協議で、相続放棄はできないんですね!?
そうです。
相続放棄をするためには、家庭裁判所での申述が必要です。
このあたりは一般の方が勘違いしやすいポイントといえると思います。
ー相続放棄と相続分の放棄とでは、手続き面以外にどんな違いがあるのでしょうか?
相続放棄と相続分の放棄は、プラスの財産をもらわないという点では共通しています。
一方、効果の面では大きな違いがあります。
相続放棄をすると「最初から相続人ではなかった」という扱いになるので、借金のようなマイナスの財産を相続せずに済みます。
一方、相続分の放棄では、マイナスの財産は相続されてしまうんです。
そのため、故人に借金がある場合、債権者から返済を求められるリスクがあります。
もちろん、相続人同士の話し合いで「債務の負担割合もゼロ」と決めることはできますが、それは債権者には関係のない話ですから。
ー怖いですね……。
ですから、「どうも借金が多そうだ」という場合は、家庭裁判所に行って、相続放棄をしたほうがいいんですよ。
「遺産分割協議書で判子を押したから」と安心していると、債権者との関係で大変なことになる可能性があります。
ープラスの財産しかなければ、特に問題はないんでしょうけど……。
プラスの財産もあるけど、マイナスの財産もあるぞというケースだと、かなり難しいですね。
そうですね。
特に注意しなければならないのは事業をやっている場合です。
法人化していればいいですけど、個人事業でやっている方は事業の関係で借り入れをしている可能性があります。
プラスの財産もありそうだけど、マイナスの財産がどれだけあるのかわからない。
これは怖いです。
ーまさに今回のようなケースですね。
そうですね。
特に今回の場合は土地が農地ということで、評価が難しいと思われます。
しかも、すぐには売れないことも多いでしょうから、きちんと現金化できるかどうか。
金融機関からの借入額と比べてみて、「本当に相続するのが得策か」を判断しなければならないでしょうね。
相続放棄の手続きと期間制限
ー特に、今回のように、プラスの財産もあるけど借金もあるらしい、という場合、相続放棄するべきかどうかの判断が難しいことがわかりました。
実際に相続放棄を検討する場合、どんな順番で手続きを進めていけばよいでしょうか。
まず、財産の内容を調査する必要がありますね。
今回のように、「いちおう家族から説明はされたけれど、不透明な部分がある」という場合は、自分でも念のために調べておいたほうが無難です。
ー相手が嘘をついている可能性があるということでしょうか?本当はプラスの財産のほうが多かったのに、「借金ばかりで大した財産がなかった」とか。
もちろんありますよ。
だから、安易に相手を信用してはいけないわけです。
相手が財産をオープンにしてくれない場合は、特に注意が必要ですね。
ー財産の調査ってどんなふうに行うのでしょうか?
まず、金融機関からの借金については、信用情報機関に問い合わせれば把握できます。
問い合わせれば、遅くとも1ヶ月くらいで結果を受け取れるはずです。
ただ、信用情報機関に問い合わせても闇金や個人間の借金はわからないので、これらの借金は督促状などから見つけていく必要がありますね。
一方、プラスの財産については、預貯金であれば心あたりのある金融機関に問い合わせて取引履歴を取り寄せる、不動産であれば記憶や固定資産税のお知らせなどをもとに登記を取って確かめる、といった手続きが必要になってきます。
ー結構大変ですね……。
そうなんですよ。
相手が財産を開示してくれない場合は、かなり大変だと思います。
しかも相続放棄には3ヶ月の期間制限がありますから、時間に余裕はありません。
ーそうですよね。
信用情報機関への問い合わせだけで、結果がわかるまで1ヶ月かかる可能性があるとなると……。
もしかして相続放棄をしようとするタイミングによっては手続きが間に合わない、ということもあるのでしょうか。
そのリスクはあります。
ただ、「相手が財産を開示してくれないので財産調査が遅れている」という事情であれば、家庭裁判所に申し立てれば期間を延長してもらうことも可能です。
実際、裁判所の方も1回くらいであれば伸ばしてくれるイメージがあります。
弁護士からひとこと
相続トラブルを避けるためには、相続人同士のコミュニケーションが重要です。
納得できないことを飲み込んでしまうと、その場は丸く収まっても、次の相続で不満が爆発する可能性があります。
相続人が互いにチェックしあい、コミュニケーションをきちんととることで、初めて健全な相続が実現できるのです。
もっとも「相手が財産を開示してくれない」「説明に不審な点がある」といった場合、当人同士の話し合いで解決するのは難しいかもしれません。
こうしたときはすぐに専門家に相談してほしいと思います。
また、借金がある場合は相続放棄も選択肢に入りますが、相続放棄は遺産分割協議で行うことはできず、家庭裁判所での手続きが必要になります。
また、財産調査の必要性や期間期限といった相続放棄ならではの問題もあります。
手続きのやり方を間違えてしまうと思わぬ不利益を被るリスクがあるため、相続放棄を検討する場合は注意が必要です。
もしわからないことや不安なことがありましたら、一度ご相談いただければ幸いです。
その他のコラム
相続放棄の落とし穴【弁護士解説】
相続放棄は相続をしないと決めることをいいます。 相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったという扱いになるため、プラスの財産を相続できない代わりに借金も相続しなくても済みます。 そのため、「故人に借金がある場合は相続放棄を選択肢に入れるべき」と那賀島弁護士は言います。 ただ、相続放棄をしようにもいろいろ落とし穴があるようで……。 そこで、今回は簡単そうで意外と難しい(?)相続放棄の落とし
モメそうな相続こそ遺言執行者を【弁護士解説】
資産が多い、相続人や利害関係者が多数いる、家族関係が複雑だ……こういった事情を抱えた相続は、たとえ遺言を作ったとしても相続の手続きが紛糾しがちです。 そこで、重要となるのが、遺言の内容を粛々と実現してくれる遺言執行者の存在です。 遺言執行者とは何者なのか、どんなときに必要なのか。 遺言執行者が必要となるケースやその仕事内容について那賀島弁護士に伺いました。 事例 私は70
兄弟が親の遺産を使い込んだ!?責任追及はできるか【弁護士解説】
「あると思っていたはずの遺産が全然ない!」となったとき、びっくりしてしまう方が大半だと思います。 実際に財産の管理をしていた人からきちんとした説明があれば納得もできるでしょうが、そうでない場合は「誰かが使い込んだのではないか」という疑念から争いになることも。 今回は、そんな「相続トラブルあるある」ともいうべき遺産の使い込み問題について、那賀島弁護士に伺いました。 事例 私(
死後の手続きはどうなる?おひとりさまのための相続入門【弁護士解説】
未婚率の上昇にともない、相続人となるべき配偶者や子どもがいない人も増加すると思われます。 こうした「おひとりさま」の場合、相続はどうなるのでしょうか。 おひとりさまをめぐる相続問題について、那賀島弁護士に伺いました。 おひとりさまの相続ってどうなるんですか? 私は現在50代後半の会社員です。 結婚はしておらず、子どももいません。 また、今後結婚する予定もありません。
老老介護から老老相続へ|相続人・被相続人ともに高齢者の場合に気を付けることは?
高齢化社会の到来により、老老介護が社会問題化しているといいます。 令和4年版の「高齢社会白書」によると令和3年10月1日現在の高齢化率は28.9%。 令和元年度の要介護認定者は655万8000人であり、主な介護者の続柄は配偶者と子どもと子どもの配偶者が半数を占めます。 配偶者による介護はほぼ老老介護に該当しますし、子どもであっても要介護認定者が80歳を超えていれば、老老介護になる可能性は大い